交通事故で負ったけがを治療しても完治せず、身体・精神に何らかの障害が残ってしまった場合、後遺障害の等級認定を受けられる可能性があります。後遺障害の等級認定を受けると、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できるようになりますが、認定を受けるには一定の条件を満たさなければなりません。
本記事では、交通事故の後遺障害に関する基礎知識や、認定を受けるための条件とポイント、基本的な流れについて解説します。
- 後遺症があるだけでは後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できない
- 後遺障害の等級認定を受けるには自覚症状や他覚症状を後遺障害診断書に詳しく記載してもらうことが大切
- 後遺障害の等級認定を受けるなら、事前に提出書類をチェックできる被害者請求がおすすめ

交通事故の後遺障害とは?
交通事故の後遺障害とは、事故で負ったけがが治療を受けても完治せず、所定の審査を経て後遺障害と認定された状態のことです。よく似た言葉に後遺症がありますが、後遺障害とは似て非なるものなので注意が必要です。
ここでは後遺障害と後遺症の違いや、認定後に請求できるもの、認定を受けるために必要な書類について説明します。
後遺障害と後遺症の違い
後遺障害と後遺症は字面が似ているので混同されがちですが、両者には明確な違いがあります。
まず、後遺症とは、継続的な治療を受けたにもかかわらず症状が完治せず、かつこれ以上治療を受けても症状の回復が見込めない状態のことを意味します。
一方、後遺障害とは、損害保険料率算出機構による審査を受け、自動車損害賠償保障法施行令(自賠法施行令)で定められた後遺障害に該当すると認められた状態を指します。後遺障害と認定されると、障害の内容・程度に応じて損害賠償請求額を決める基準にもなる等級(1~14級)が付与されます。
なお、後遺症があっても、後遺障害と認定されなければ後述する後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求できないので(請求しても原則として認められませんので)、注意が必要です。
(参考:e-Gov法令検索 『自動車損害賠償保障法施行令』)
後遺障害等級認定されたら請求できるもの
後遺障害の等級認定を受けると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できるようになります。
後遺障害慰謝料とは、後遺障害を負うことによって受けた精神的な苦痛に対して支払われる慰謝料のことを意味します。後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて算出され、障害の度合いが大きい(等級が1に近い)ほど金額も大きくなります。
なお、慰謝料の算定に用いる基準には自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがありますが、原則として、弁護士基準を用いた計算が最も高額になります。
後遺障害認定を得るために必要な書類
後遺障害認定を得るためには、以下のような書類の提出が必要になります。
- 後遺障害診断書
- 支払請求書
- 診療報酬明細書
- レントゲン写真、МRI画像等の検査結果書類・データ
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 印鑑証明書
- 休業損害関連書類(休業損害証明書や源泉徴収票、納税証明書など)
- 通院交通費明細書
- 付添看護自認書
これらの書類は状況に応じて要不要に違いがあります。また、状況によっては上記以外の書類の提出が必要になる場合もあるので、審査を行う損保料率機構調査事務所に問い合わせて事前に確認しておくのが無難です。
なお、事故の相手方が加入する任意保険会社を通じて申請する事前認定の場合、被害者側は後遺障害診断書を同任意保険会社に提出するだけで足ります。
(参考:国土交通省『自賠責保険金(共済金)支払までの流れ』)
交通事故の後遺障害等級認定を受けるための条件
交通事故で負ったけがについて後遺障害の等級認定を受けるには、一定の条件を満たしていなければなりません。条件は複数あり、いずれか一つでも該当しない場合は後遺障害認定を受けられないことになるので、注意しましょう。
ここでは後遺障害認定を受けるために必要な条件を5つご紹介します。
症状と交通事故に因果関係がある
交通事故で後遺障害を負ったと認められるためには、当然ながら、その症状と交通事故の間に因果関係があることを証明しなければなりません。そのためには、交通事故が発生した後、速やかに医療機関を受診し、必要な診断・治療を受ける必要があります。
事故発生から受診までにある程度の期間が空いてしまうと、そのけがの原因が事故によるものと立証するのが難しくなる場合があるので、注意しましょう。
特に、むちうちなどのけがは事故発生からしばらく時間が経過した後になって痛みやしびれが出てくること(痛みやしびれに気づくこと)があるので、事故直後に異常がなかったとしても、少しでも違和感があるならば、念のため受診しておくことをおすすめします。
症状が一貫して継続的に現れている
後遺障害と認定されるためには、原則として、治療を続けても完治せず、症状が残っていることが必要となります。事故発生時から一貫して同じ症状が継続して現れていなければ、症状が残っているとはいえません。治療を続けているうちに症状がなくなった、事故当初と異なる症状が出たなど、症状に継続性や一貫性がない場合は後遺障害と認められない可能性が高くなります。
特に、治療を担当する医療機関が途中で変わった場合、医師の所見が変化してしまうことも考えられるので、転院する際はこれまでの症状や、受けてきた治療についてしっかり説明することが大切です。
症状を医学的に証明できる
けがの症状には、被害者が自身で感じている痛みやしびれといった自覚症状と、医師の視診や触診、画像診断などによって医学的に証明できる他覚症状の2種類があります。後遺障害の認定を受けるには、自覚症状のみでは不十分で、他覚症状も認められることが必要です。
体の一部が欠損している、あるいはレントゲンなどの画像検査で異常が確認できる場合は容易に証明できますが、中には他覚的に症状を証明するのが難しいケースもあります。その場合は、医師の指示に従ってCTやMRIといったより精密な画像検査や神経学検査を受け、他覚的症状があることを立証できるよう努めましょう。
後遺障害等級の認定基準を満たしている
後遺障害認定では、後遺障害の内容や度合いに応じて1~14までの等級が設定されています。交通事故で負ったけがが1~14等級のいずれかの症状に当てはまっていないと、後遺障害の等級認定を受けることはできません。
後遺障害等級の概要は国土交通省のホームページなどで公開されている後遺障害等級表に記載されているので、自身のけがの症状が1~14等級のいずれかに該当するかどうか事前に確認しておきましょう。
自身の症状が後遺障害等級に該当するかどうかが分からない場合は、後遺障害認定に詳しい弁護士に相談してアドバイスしてもらうことをおすすめします。
(参考:国土交通省 『後遺障害等級表』)
治療期間が適切である
後遺障害認定では、事故によって負ったけがが治療を続けても完治しなかったことを証明する必要があるため、一定以上の期間にわたって治療を継続しなければなりません。
認定に必要な通院日数は明確に定められていませんが、後遺障害14級の認定を受けるには、原則として通院期間6カ月以上、通院日数60日以上が必要といわれています。通院期間6カ月の間で通院日数60日以上という条件をクリアするには、毎月10日以上(週に2~3回程度)は医療機関で治療を受けることになります。
治療期間が短い場合や、通院の間隔が空きすぎている場合、通院が不定期な場合(例えば、最初の1か月は月に20日通院し、その翌月には5日通院したものの、3か月目には25日通院したような場合)は適切な治療を受けなかったとみなされて、認定を受けられなくなるおそれがあるので、注意しましょう。
交通事故の後遺障害等級認定を受けるためのポイント
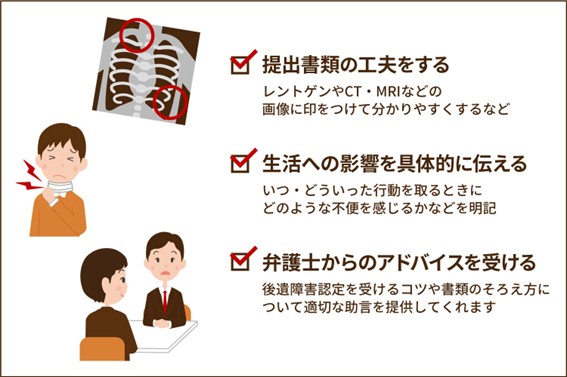
交通事故で後遺障害認定を受けるのは簡単なことではありません。2022年度における自賠責保険の支払件数は84万2,035件、後遺障害等級認定件数は3万7,728件であることから、後遺障害認定率はわずか4.4%程度であることが分かります。
認定される可能性を少しでも高めるために、申請する際は以下のポイントを押さえておきましょう。
- 提出書類の工夫をする
- 生活への影響を具体的に伝える
- 弁護士からのアドバイスを受ける
(参考:損害保険料率算出機構 『2023年度版自動車保険の概況』p24、p40)
提出書類の工夫をする
後遺障害等級認定の審査は、基本的に提出された書類を基に実施されます。そのため、提出書類に記載漏れなどの不備はないか、入念にチェックすることが大切です。
また、レントゲンやCT、MRIなどの画像には、異常があった部位が一目で分かるよう、○印などをつけるといった工夫を施すのも有効な方法の一つです。
うっかり見逃してしまいそうな小さな異常に関しては、医師から詳しい説明を受けた上で、その場で印をつけてもらってもよいでしょう。
生活への影響を具体的に伝える
後遺障害を負うと、仕事や日常生活に少なからず支障を来します。いつ・どういった行動を取るときに・どのような不便を感じるかなどを明記しておけば、後遺障害が存在することをアピールできるので、医師に後遺障害診断書を作成してもらう際は、なるべく具体的な状況をわかりやすく伝えるようにしましょう。
特に、他覚症状の乏しいけがに関しては、日常生活に影響を及ぼす症状があることを訴えることで、後遺障害認定を受けられる確率が高くなります。
なお、自身の説明だけでなく、同居している家族の証言などもあればより信ぴょう性が増すでしょう(同居の家族にお願いして、陳述書を作成してもらうことは少なからずあります)。
弁護士からのアドバイスを受ける
後遺障害診断書をはじめとする各種提出書類は、書き方一つで相手(損害保険料率算出機構)に与える印象が大きく変わります。
特に、後遺障害診断書については、可能な限り具体的な症状や状況を記載することが重要なポイントになるので、医師への症状の伝え方には十分な注意を払う必要があります。
「医師にどのように伝えればよいか分からない」「不備のない書類を揃えるには、どういった点に気を付ければよいのか分からない」など、提出書類に関して疑問がある場合は、後遺障害の等級認定に詳しい(交通事故事件の経験が豊富な)弁護士に相談してアドバイスをもらいましょう。
豊富な知識と実績を持つ弁護士であれば、後遺障害の等級認定を受けるコツや書類の揃え方について適切な助言を提供してもらえるので、認定率の向上を期待できます。
交通事故の後遺障害認定を受けるまでの流れ
交通事故の後遺障害認定を受けるには、然るべき治療を受けた後、後遺障害診断書の作成や申請手続などを行う必要があります。
症状固定の診断を受けた日から認定結果の通知を受ける日までには、ある程度の期間を要するので、なるべくスムーズに認定を受けられるよう、大まかな流れをチェックしておきましょう。
症状固定の診断を受ける
症状固定とは、それ以上治療を受けても症状の改善や回復を見込めないと判断された状態のことです。
後遺障害認定では、交通事故で負ったけがをが治療しても完治せず、症状が残ったことを証明しなければならないため、まずは医師から症状固定の診断を受ける必要があります。
いつ、どのような状態をもって症状固定と診断するかは、リハビリ後の症状や骨癒合の状態などを基に医師が決定しますが、痛みやしびれなどの症状は被害者本人しか分からないものなので、医師と相談しながら治療を進めていくことが大切です。
なお、一般的な症状固定のタイミングは、通院の頻度等にもよりますが、むちうちや骨折後に残った痛み、ケロイドなどの症状については半年以上、高次脳機能障害については1年以上がおよその目安とされています。
後遺障害診断書を作成してもらう
医師に症状固定と診断されたら、後遺障害診断書の作成を依頼します。
後遺障害診断書には主に以下のような項目を記載します。
- 被害者の氏名・住所・生年月日など
- 受傷した日時
- 症状固定日
- 入通院期間
- 傷病名
- 既存障害
- 自覚症状
- 他覚症状および検査結果
- 障害内容の増悪・緩解の見通し
- 医師の署名
このうち、特に重要なのは7~9です。ここに記載されていない症状は存在しないものとみなされるので、記載漏れに注意するのはもちろん、なるべく具体的かつ詳細に記載してもらうことが大切です。
なお、診断書は医師でないと作成することはできません。治療の一環として接骨院や整体院に通っていた場合でも、診断書の作成は整形外科などの医師に依頼する必要があります。
事前認定か被害者請求にて申請する
後遺障害の等級認定の申請方法には、事前認定と被害者請求の2つがあります。
事前認定は相手方の任意保険会社に申請を代行してもらう方法で、同保険会社に後遺障害診断書のみを提出すればよいので、手続の手間を省けるところが利点です。ただ、他の書類を事前に確認することができないため、不備があっても気付けないというデメリットがあります。
一方の被害者請求は、被害者自身が書類の準備から申請まで、全ての手続を担当して行う方法です。かなりの手間と時間を要しますが、書類を事前に精査できるので、認定に有利になる証拠や書類などを任意で追加できます。
また、被害者請求をした場合、示談の成立前に先払い金や仮渡金を受け取れるところも大きな利点です。
どちらも一長一短ですが、後遺障害の等級認定を受ける確率を上げたいのなら、被害者請求を選んだほうがよいでしょう。
認定結果が通知される
後遺障害の等級認定の申請を行うと、提出された書類を基に損害保険料率算出機構が審査・調査を実施します。提出された書類だけで十分に事実確認ができない場合には、医療機関に対する治療状況の照会など、必要に応じた調査を行うこともあります。
また、特に慎重かつ客観的な判断が求められる事案(特定事案)で行われるのは、外部の専門家を交えた専門部会による審査です。例えば、後遺障害の内容が脳外傷による高次脳機能障害、あるいは非器質性精神障害(脳の損傷を伴わない精神障害)に該当する可能性がある場合は、後遺障害の専門部会にて審査を実施するケースがあります。
一般的に、後遺障害の認定期間は1か月程度とされていますが、審査や調査が長引いた場合は1か月以上の時間がかかることも珍しくありません。
審査が終了したら、被害者宛に認定結果が通知されます。なお、結果に不服がある場合は異議申し立てを行うことも可能です。
まとめ
交通事故で後遺症が残ったら、所定の審査を経て後遺障害の等級認定を受けられる可能性があります。後遺障害の等級認定を受けると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などを請求できるようになりますが、けがと事故の因果関係の証明や適切な期間の通院など、一定の条件を満たしている必要があります。
また、条件を満たしていても、書類に不備があれば認定を受けることができないので、弁護士からアドバイスを受けながら準備を万端に整えて申請することが大切です。
琥珀法律事務所では、後遺障害認定のご相談を含め、交通事故の補償問題を数多く取り扱ってきた実績があります。
後遺障害認定を受けることを検討されている方や、ご自分の症状が後遺障害に該当するか悩んでいる方は、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。

【経歴】
| 2008年 | 弁護士登録 |
| 2010年 | 主に労働事件を扱う法律事務所に入所 |
| 2011年 | 刑事事件、労働事件について多数の実績をあげる |
| 2012年 | 琥珀法律事務所開設東村山市役所法律相談担当 |
| 2014年 | 青梅市役所法律相談担当 |
| 2015年 | 弁護士法人化 代表弁護士に就任 |
| 2022年 | 賃貸不動産経営管理士試験 合格 2級FP技能検定 合格 宅地建物取引士試験 合格 |
| 2024年 | 保育士試験 合格 (令和5年後期試験) 競売不動産取扱主任者試験 合格(2023年度試験) |
| 2026年 | 貸金業務取扱主任者試験合格(2025年試験) |
【その他のWeb活動】
- ブログ:弁護士川浪芳聖の「虎穴に入らず虎子を得る。」
- Facebook:川浪 芳聖のフェイスブックページ


